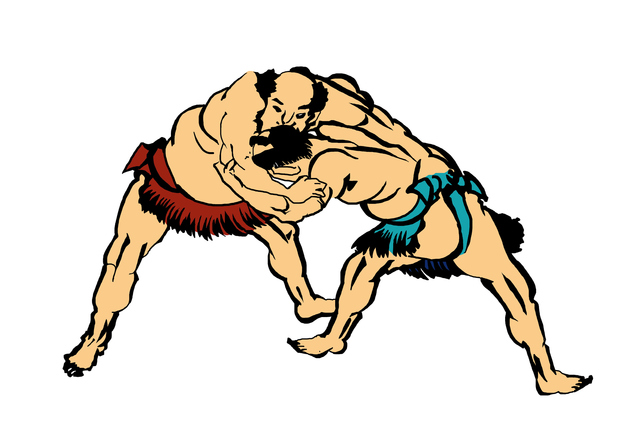
現在、参集殿の地にあった土俵の上に大提灯が飾られ、その下で「こんぴら相撲」が開催されておりました。横綱から十両まで勝敗が決められ、勝った力士には景品も振舞われ、こんぴら相撲には人気がありました。
時代が進み江戸時代には雪害や日照りで年貢が納められない仕儀になった時、倹約令が交付され贅沢は厳しく禁止されました。
当地の代官はこんぴら祭りを取り締まり「相撲などと言う娯楽を日中堂々と行うのはけしからん。楽しみ事は夜間行え」と言われました。困った神社側は、大きな提灯を作り小さな提灯も周囲に飾り日中堂々と相撲を行いました。
代官のイキなお裁き「夜間を模して行うなら」

代官に「このお山には高い木が生えていて暗いので今は夜であるかと思いまして・・・」と恐る恐る申しましたところ窮地に立った代官は「夜間を模して相撲を行うは可なり」という粋なお裁きが出て以来誰からともなく「提灯相撲」としてもてはやされたと言われます
戦時中物資不足の折にこの相撲は中断を余儀なくされました。今尚この相撲を懐かしむ声が折々に聞かれ拝殿に設置されている大提灯がこの歴史を物語っております
皆様の生業が続く限りこんぴらさん信仰は不可欠なものであると信じます。眼下で力を鼓舞した男たちの勇壮な行いを御理解頂き、金刀比羅山宮が鎮まる限り、継承し設置させて頂くべきものと心得たく存じます。(写真は旧・大ちょうちん=昭和29年謹製=)